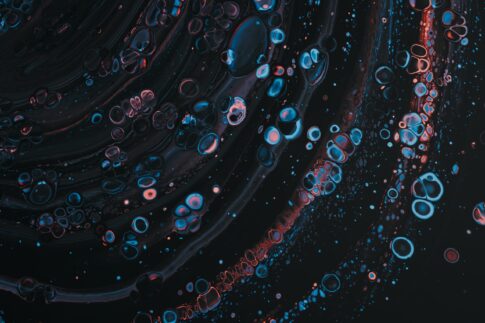The Limbo of Empathy
幕間.meets girl:迷い子
The Limbo of Empathy ‐ 目次
幕間.meets girl:迷い子
下校の途すがら、交差点へ差しかかった。夕日が一帯を黄色くする様な頃合いだった。
信号が赤だったので、私は電柱の傍に立って往来を行き交う車の流れをぼんやりと眺めていた。プリウス、フィット、ワゴンR、プリウス、タクシー、ポロ、ラパン、アクア、エクストレイル、Bクラス、ジムニー、プリウス、リンカーン、サンバー、……。
リンカーンが何故と思った拍子にスカートの裾が引かれた。見ると足許にちいさい女の子がいた。
信号が青に変わり、通りゃんせの音楽と共に身の回りが雑踏し出した。私はその場に留まって女の子を見ている。保育園や幼稚園のものと思われる制服を着て、ベレー帽をかぶっている。ぼんやりとした顔だが、恐らく私の顔もぼんやりとしているだろうから人の事は云えない。女の子は矢張りぼんやりとした声で、「ここどこ」と云った。
私は構わず横断歩道を歩いた。ここの信号は長いのでさっさと向こうへ渡ってしまいたい。人波に起こる色々の音が、靴音や話し声、何かを運ぶ音が混雑する中で、私の後ろをついて来るちいさい足音が微かに聞こえた。
信号の点滅を眺めながら歩道へ入り、少しばかり歩いた所で後ろを振り返った。先程の女の子が足許にいた。先程と同じ様なぼんやりとした様子で人の顔を見ている。「お腹空いた」と云って片頬を膨らますので、私は観念した様な気持ちになった。
先日久保が美味しいと話していた洋菓子店に入って、モンブランを買った。ひとつ七百円もする高級品だった。お会計を済ませ、ショーケースに顔をくっつける女の子にちいさく「行こう」と云った。店を出ると手を握って来た。ちいさい手だった。ぷにぷにと柔らかい手だったから、私にはそれが心地よく、感触を味わう為に歩きながら何遍も握った。
「食べたい早く。ケーキ」
「着いたら食べよう」
道の先に花屋があったので寄って見た。花を包んで貰っている間、私は店の前にある長椅子に女の子と一緒に腰かけて、往来を眺めていた。黄色い脚を伸ばしていたお日様も段々と傾いていると見えて、向かいのビルの、更に向こうに見える空の奥はもう紺藍色に入り、宵の明星が細い光を瞬かせている。
「お星様」と女の子が云った。
「そうだね」と応えながら、私はぼんやりと星を眺めている。
「もう直ぐ夜が来るから、お星様が来たんだよ」
「そうだね」
「こと好き。お星様。でもママが、暗いとお外に出たら駄目って云うから、お家でお星様の絵本見るの」
「そうだね」
「暗くなるから、お家帰る」
「そうだね」
夜の気配が見えはするが、残暑の日は未だ長い。曖昧な時間が続くのが私は好きだった。もう間もなく、空は明るいけれど身の回りは暗いと云った時間が来る。向こうから来る人の顔がよく解らないから、その様な時間の事を古来人は誰そ彼と呼んだ。電気や外灯がない時代であれば尚更解らないだろうが、解らないままの方がいいと云った事もある。口裂け女の話の教訓は、マスクには美顔効果があると云う事である。
花が出来たので受け取りを済ませ、再び往来へ出た。女の子の名前は琴乃と云った。私の住む家からそれ程遠くない所に暮らしていたので、付き合いが深い訳ではないけれど、ことちゃんの親御さんも含め知らない間柄ではなかった。ことちゃんが私を知っているのかは知らないが、私はこの子がベビーカーに載せられていた頃から知っている。家に帰りたがっているのであれば返してやるのが真当だろう。よく迷子になる子だと思った。
そうして人通りの多い往来を抜け、ことちゃんの家へ続く筋に入った。途中に私の家があるが、もっと向こうなので一旦素通りする。立ち並ぶ家々から夕餉の支度をする気配が流れて来る。空の紺藍色はその領域を広げ、少しずつお日様を地平線に仕舞おうとしている。随分増えた星々の控えめな光が、却って一帯の影を濃くする様に思われた。星に纏わる絵本の様なものは家にあったか知らと考えている。漢字があるとこの年齢では自分で読めないだろうから、詩集は難しいかな、図鑑なら絵とか写真があるからセーフかな、なぞと云った事ばかりが頭の中を巡っている。
「お家」と云ってことちゃんが指差した。考え事をする内に到着したらしい。
「うん」
「お姉ちゃんありがと。ケーキ食べたい」
「うん」
インターフォンを鳴らすと奥さんの声で応答があった。自分が近所の鮎川である旨を伝えた。
「宇美ちゃん。どうしたの?」
エプロンで手を拭きながら、奥さんは何でもない風に玄関から出て来た。
「忙しい時間に、済みません。これ。ことちゃんに」
「まあ」
家に上がり、仏間へ通された。私は仏壇にモンブランと花を供え、線香を上げた。手を合わせていると奥さんが来て、「いつも有難うね」と云った。
「もう四年になるのね。時間が癒やしてくれるって皆云うけど、こればっかりは駄目ね。ずっと。今でも昨日の事みたいに思い出すわ」
出されたお茶を頂きながら、奥さんの話を聞いた。言葉とは裏腹に、事実をすっかり受け入れている様に思われた。しかしそれは慣れるだとか、忘れるだとか、そう云った事では断じてない。この事実を終生背負って行く覚悟を決めた母親の美しさを、ここに来るといつも目の当たりにする。
「今日の琴乃は、どんなだった?」
「はい。相変わらずでした」
奥さんは「そう。よかった」と云って少し笑った。
「今日は手を繋いで帰りました。……。今なら」
私は奥さんと向かい合って坐り直した。
「手を、……」
触れないように気をつけながら、私は両掌で鞠を持つ要領で、差し出された奥さんの手を包む様な格好を取った。
日が暮れたらしく、明かりをつけずにいた仏間は薄暗い。線香のにおいが鼻先を掠めた。私は奥さんと呼吸を合わせた。そしてまばたきを合わせ、体温を合わせ、脈を合わせ、内臓の状態を合わせ、ニューロンの神経インパルスの入出力を合わせる。
「あっ」
不意に奥さんが声を上げた。
「解る。解る。……。琴乃なの? 琴乃。琴乃の手が。柔らかい。琴乃。ああ、……」
濡れた睫毛の下で自分の震える掌を一心に見詰めながら、何度も娘の名前を呼んだ。
奥さんに見送られながら、私は自分の家路に就いた。
今直ぐ走り出したい思いに駆られる。あんな事、金を取らないだけで詐欺師やカルトの教祖と同じではないか。全く自分の幻覚や妄想に過ぎないものを当事者に押しつけてどうする。ことちゃんはあの交差点で死んだ。それで仕舞いだったのに、いつまでも蒸し返す様な真似をする自分に嫌気が差す。あそこを通る度、抑えが効かなくなってしまう。何の事はない、囚われているのは私の方で、あの美しい奥さんの心を乱した挙げ句、善行をした様な気になっている。もう辞めようと思う。金輪際あんな事はしない、ことちゃんの事も見ないと自分に云い聞かせる。
「お姉ちゃん」
背後で声がして、スカートの裾が引かれた。
「ケーキ美味しかった。ありがと」
身の回りは夜気に満ちている。いつの間にかまんまるのお月様が出ており、こうこうと光って辺りを照らしている。
「またね」
やっとの思いで振り返った拍子に、私は自分が涙を流している事に気がついた。