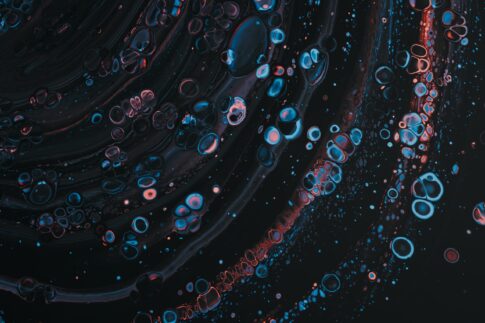The Limbo of Empathy
introduction:序
The Limbo of Empathy ‐ 目次
introduction:序
長い汗が首を辷り落ちた。
直ぐに薄い風が吹いて汗の跡を乾かした。
いつも通る通学路を外れて、人気のない路地を歩いている。石垣に苔が生している所に青いもみじがかぶさっている。隅に水の入っていない手水鉢が転がっており、その上で白猫があくびをしている。夏の終りが近づいているが、暑さは少しも和らがず、ずっと向こうに見える路地の終わりで逃げ水が立っている。あんまり眩しいので、あそこに出て行かなければならないのかと思うと気が滅入って来る。
近頃ルーティーンを変えなければならないという強迫観念に近い衝動に駆られる。ルーティーンとは、自分を自分たらしめるゲシュタルトであると同時に、自分は自分より外のものにはなれないという枷でもある。同じことを続ける限り同じ自分が明日も続いていくから、昨日の自分以外の何かになろうとする時、昨日の自分が行なっていたルーティーンを変えなければならない。それが私にとっては通学路から外れると云うことであり、これをきっかけにしてもっと色んな物事を変えて行きたいと思う。正直な所、この薄暗い路地、残暑から取り残された様なその風情に、かなり緊張している。
夏休みが明けたので、私の高校生活は二年目の第二四半期を無事に終えようかと云った段になる。このまま平穏な学生生活を送り、それなりの大学に入って、司書とか学芸員の様なものになりたいと思っている。昔おさるのジョージが大好きで、黄色い帽子のおじさんに憧れていた。今も憧れている。あんな風に文化的な生活を送って行きたい。私は刺激を欲しない。起伏のない暮らし、波風の立たない心の森閑とした中で生きて行きたい。しかし昨日までの私では黄色いおじさんになれない。だから黄色いおじさんに近づくための刺激を受けなければならない。何かを変えなければいけないと思うけれど、何を変えていいのか解らないから、思いついたものを何でも変えて見る。嫌だけど。
校門を抜けて、下駄箱で靴を脱いだ。金髪になっている生徒を見て、その手があったと思った。私はこの夏休みに何をやっていたのだろう。宿題を終えた後は大和古寺風物詩を三回読んで、一千一秒物語を六回読んで、室生犀星集を二回読んで、クリスマスの思い出を一回読んで、七つの夜を三回読んで、夫婦茶碗を三回読んで、フィネガンズ・ウェイクを十四回読みかけたけれど結局読めなかった。もっと髪やピアス、酒、タトゥー、煙草、変な薬など、その様なものに目を向けるべきだった。何故夫婦茶碗を読んだ折に気がつかなかったのか。
教室へ入ると久保が来た。
「転校生来るらしいよ」
再会の挨拶もそこそこに云うから、
「ほほう」
「それがさー、さっきアキとかと見に行ったんやけど。ムフフ。これが中々」
「ほほう」
自分の席に就いて、久保や萬谷と取り留めのない会話をする内に朝礼の時間になったらしく、教室の手前の扉を開けてマックが入って来た。
「マック転校生は?」
「マック久しぶり転校生は?」
生徒達が押し寄せて口々に云うので、
「おめーら席就けって。はい」
マックは手を叩いた。
「皆さんが席に就いて静かにするまで先生転校生とか紹介しないもんねー」
「うざ」
静かになったので、マックは教室の外へ出ると二名の生徒を連れてまた入って来た。
ひとりは細身、ミディアムマッシュ、糸目の優男で、もうひとりはアップバングで格闘家然とした、体格のいい精悍な男だった。
俄に女子の間に色がついた様に思われた。転校生が二名もいると云う事もそうだが、信じ難い事に、この二名の風貌で以て恐らくクラスの女子の好みの殆どを網羅している。
「藤沢です」
黒板に名前を書いて、糸目の男が云った。
「藤沢伸です。大阪から引っ越して来ました。仲良くして貰えると嬉しいです。よろしく」
関西弁を出さない為に敬語なのだろうかと思う。人畜無害と云った印象だけれども、弱々しさはない。
「籐堂だ」
今度は体格のいい男が見た目通りの声で云った。
「籐堂誠司。生まれは仙台。親の転勤について来た。柔道をやってる。勿論柔道部に入る。座右の銘は一投入魂。よろしく」
「藤かぶりやなー」
藤沢が藤堂の脇をつついた。
「てか一投入魂て、野球やないかい」
「藤沢が関西人で助かった。転校初日から渾身のボケスルーされて死ぬかと思った」
教室のあちこちで笑いが起こった。恐らく二人共元の学校ではスクールカーストの上位存在だったのだろう。この余裕。とんでもない人材が来たものだと思った。
「シンちゃんて呼んでや」
「掴みはばっちりだなお前ら。みんな仲良くしてくれよー」
マックはこちらの方を指差した。
「じゃ、とりあえずあそこの空いてる席坐って。直ぐ席替えするけど」
何故か私の両隣の席が空いている。陰謀かと思った。若しくは私の潜在意識にある願望の様なものが顕在化したのではないか。
「教科書とか届くまでは、鮎川が見せてやってくれよー」
暢気な調子で云うマックの声と、私に注がれる女子の視線が対象的だった。
「鮎川さん、よろしく。下の名前なんて云うん」
藤沢が早速話しかけて来た。
「よろしく。……。宇美」
「おしゃれな名前やなあ。ウミちゃん、ウミちゃんなー」
にっこりとしながら耳許の髪をかき上げた。ピアスの穴が幾つも空いている。
「あ。改めてよろしくな、藤堂。なんて呼ばれてたん」
私を挟んだ向こうで藤堂が腕を組んでいる。
「よろしくシンちゃん。トウドウとかセイジ。月並みだな。鮎川さんもよろしく。クラスの柔道部って誰か解るか」
実直や正道と云った印象だったけれど、藤堂から微かに香の香りがした。いい匂いだと思った。初対面から数分しか経っていないにも関わらず、二人共ここまで人に好感を抱かせる事が出来るのかと思う。私は自席で固まっていた。情けない話だが、緊張していた。二人をまともに見られないから、臍の辺りで両掌を組んだなりで俯いている。先程久保と転校生について詮索していた頃を懐かしく思う。
「あの。……」
二人の視線がこちらへ向けられたのが解る。
「あの、案内。二人共、えっと、学校案内する。私が。後で、休憩、の時とか」
昨日までと同じこと、同じ思考、同じ行動を続ける限り、昨日までの自分と同じなのだから、過去の自分がしない事を行わなければならない。今朝の通学路を外れた際の決意を、こんな所で曲げる訳には行かない。黄色い帽子のおじさんになる為には、経験を積まなければならないと、確信に近いものを持っている。
お午休みになったので、私は二人を引き連れて教室を後にした。廊下にも転校生をひと目見ようと生徒が押しかけており、教室の内外の視線が痛いが、私は威張って売店、学食、特殊教室、図書室、体育館、武道場、校庭、中庭と云った施設を巡った。最後に人気のない一階の渡り廊下の自販機に来た。幽霊が出るとの事で余り生徒が寄りつかず、いつも静かなので気に入っている。私は缶コーヒーを三本買うと、その内の二本を二人に渡した。
「……。これ。奢り。今日は」
二人は吃驚した様な顔で受け取った。
「ごめん。無理矢理連れ回しちゃって。あの、外のみんなと喋ったりとかしたかったよね。ごめん。私この通り根暗で、教科書とか見せるなら、色々この学校の事、教えといた方がいいのかなって、ひとりで暴走してしまった」
藤沢が私の頭をぽんぽんと優しく叩いた。
「おもろ。コーヒーまで奢ってもろて、感謝しかないやんか」
「ん。お陰で大体解ったし、こっちこそ手間をかけさせて済まん」
近くのベンチに腰かけて、藤堂はくつろいだ様子でコーヒーを飲んでいる。それだけだったが、見惚れる様な佇まいだった。藤沢は気にしいやなあと云いながら今も私の頭を撫でている。手を退けて欲しいと思う。不快な訳ではないが、耐性のない者にとっては非常に刺激が強い。この距離感は私のこれまでの人生にないものだった。
私は手許のコーヒーを流し込んだ。苦かった。間違ってブラックを買ってしまった。
「外の女の子と何かあったら云うてや」
教室へ帰る途すがら藤沢が云った。
「云うたら何やけど、俺結構モテるから。セイジもやろ」
「俺は別に。だが俺達のせいで鮎川さんに迷惑がかかるのはよくないな」
そんな事まで気にかけてくれるのかと思った。
「私は。大丈夫。多分」
その日の行程が終わり、放課となった。私は自分の席に就いたままぼんやりとしていた。今日は疲れた。何かの自己啓発本の様なものに、自分の行動を変えるには環境が変わるのに合わせるとやりやすいと書いてあった。私にとってはそれが夏休み明けだと思っていたから、努めてその後の事や余所様にどう見られるかは考えないようにしていた。にしても疲れた。帰りたいが、腰が重い。このまま眠ってしまいそうだった。
「えらいお疲れやねえ」
藤沢が頬杖をついたなりで云った。私は半分目を瞑りながら、
「藤沢君、部活とかしないの」
「シンちゃん呼んだってや。帰宅部オーケーなら帰宅部でええかなあ。前のガッコは帰宅部あらへんかったから、茶道部」
私は少し笑った。藤堂は既に柔道部の入部手続きに向かっていた。外の生徒は皆各々の友人同士でお喋りをしたり、こちらの様子を伺ったりと云った塩梅で、いつまで経っても教室はなんとなく混雑した様な気配で満たされている。
「私はぼちぼち帰ろうかな」
本当は少し眠ってしまいたいが、その様なお行儀の悪い姿を藤沢に見せる訳には行かない。
「藤、シンちゃんと話したい子多いだろうし」
「ちゃうねん」と云って藤沢は頭を掻いた。
「どっちか云うたら男友達が欲しいねんなー。セイジが一号で。女の子とばっか絡みよったらアカンやろ。その辺の立ち回り上手い事やらななあ。せやから取り敢えず、女友達はウミだけでええかな思とる」
「そなんだ」
私の席に三名の女生徒がやって来た。皆知らない顔で、なんとなく険しい様な表情だった。金髪ゆるカール、黒髪外ハネボブ、ショートボブインナー金髪と云った出で立ちで、非常に参考になる。
「鮎川さん、よね」
金髪ゆるカールが云った。
「今大丈夫?」
いい匂いがする。
「はい。大丈夫です」
「あたしレイミ。三年。後輩に鮎川さんの事聞いてさ。バレー部の梶原」
「あー。梶原さん」
「ちょっと話があって。時間あるなら場所変えない?」
「大丈夫ですよ」
「それ、俺も行ってええやつ?」
藤沢が割って入って来た。
「……。誰?」とレイミさんが返した。
「あれ?」
恐らく藤沢は何か思い違いをしているのだろうと思う。これから私が不利益を被る事になると考えているのだろう。表情や振る舞いに出さないが、その様な気勢が感じられる。自分でモテると云うだけの事はある。しかしどうしようか。遅かれ早かれ知られる事にはなるだろうし、それが今日だとは思わなかったけれど。
「シンちゃん。時間ある? 助手なんです。矢っ張り男手が必要な事もありますし」
そう云う事ならと、レイミさん達は納得したらしかった。藤沢の方は合点の行かないなりで「ええよ。暇やし」と云って同行する運びとなった。
学校の近所のタリーズに入って、飲み物を買って席に就いた。レイミさんの外の二人は付添いらしく、深刻な顔をしてストローを咥えるだけだった。
「それで、お話と云うのは」
「結論から云うと」
レイミさんはしっかりと私と目を合わせて来た。カラコンを入れているが、その向こうに広がるレイミさんの景色を見た。眠い。しかし却ってその方が都合はいい。
「あたしに憑いてる幽霊を何とかして欲しい」
横の藤沢が咽せかけたと見えて、ちいさく「ん」と云った。
「解りました」
困惑や動揺、疑念、不審など、その他諸々の感情がいちどきに押し寄せて、そして離れて行くのが当たり前だった。オカルトや宗教の類と云って差し支えないだろうと思う。藤沢は感情を出さない。この一日で解った。押し隠し、閉じる事にかけては達人と云えるから、だからこそこの場への同席を許した。遅かれ早かれ解る事だから、これから起こる事を藤沢自身に解釈して貰い、判断して欲しいと思う。しかし折角のイケメンだし、これで駄目になるにしても、もう暫く友達でいたかったな。
「時と場所を決める為に、何かきっかけがあれば教えて貰えませんか。それから今何が起こっているのか、なるべく詳細に」
タリーズを出る頃にはすっかり日が落ちていた。送ってくれると云うので藤沢と夜の往来を歩いている。
「色々纏まりきらへんねんけど。ウミってアレなん? 霊能者?」
「ううん」
「どないすんのこれ」
「どうにかするよ」
熱帯夜は未だ続くらしく、首許を擦り抜けていく風、また制服の袖口に辷り込んで来る風、汗ばんだ掌を乾かす風、皆なんとなく締まりがない様で覚束ない。私は秋が好きだから、早く秋になって欲しい。そして冬は嫌いなのでそれきり冬が来ないで欲しい。
「うーん。見えへんな。話が」
「先輩が云った通りなんだと思うよ」
「いや、ウミに相談してどないすんねん、て話」
「シンちゃん」
私は立ち止まり、藤沢を見た。藤沢は振り返りかけたなりでこちらを伺っている。
「私は幽霊とかお化けとか、妖怪とか信じてないよ。別に。でも夜のお墓はこわいし、ホラー映画もこわい」
レイミさんの表情が思い出された。瞳を潤ませ、震えていた。
「その上で、先輩の話は真実だと思う。私は信じる。幽霊や妖怪は信じないけど、先輩の話は信じるよ。先輩が見たならそうなんだと思う。先輩が見たのと同じものを私も見る。それから、どうにかする」
「なんや、雲掴む様な話やなあ」
「正直引いてると思うけど、興味あったらその時に、その場所に来て欲しい。多分、見せられると思うから。シンちゃんにも」
自宅の近所の辻で藤沢と別れた。何かを変えると云う事は非常に難しい。自責にしろ他責にしろ、偏るのはよくないと思う。大切なのはバランスで、自分でも変えたいと思って変わるように動きつつ、変えてくれそうな人や環境にはしっかりと頼る事が肝要と悟った。なんだか今日は永い一日だった。私にとってはレイミさんからの相談内容よりも、転校生二人との関わりの方が遥かに大きな問題だった。一日の終りにレイミさんから声をかけられた時、私は内心安堵していた事を告白しなければならない。